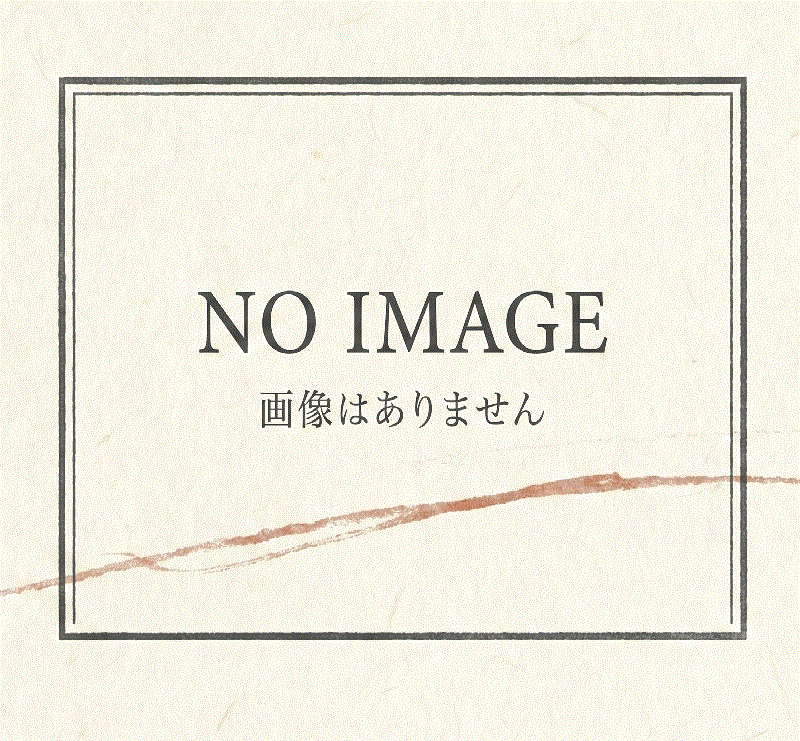技法・素材
中谷有逸は、生涯を通じて「単純なかたち」と「複雑で触覚的なマチエール(質感)」の両立を追求した。
その表現を支えたのは、1960年代に自ら開発した独自の版画技法「凹凸併用版(おうとつ へいようばん)」と、
病を経て到達したステンシル(合羽版)による重厚な表現、そして十勝の風土そのものを画材として取り込む自家製インクである。
中谷の制作は、一枚の絵ではなく「素材と向き合う時間の積み重ね」を重視したものであり、 大地・鉄・炭・紙・木――あらゆる物質が、彼の内部に蓄積された記憶と共鳴しながら「碑(いしぶみ)」のかたちへと結晶していった。
I. 凹凸併用版(おうとつ へいようばん)
1960年代半ば、中谷が模索の末に独自に生み出した版画技法で、以後30年以上にわたって代表作の基盤となる技法である。
従来の版画は、凹部(エッチングなど)か凸部(木版画など)のどちらか一方にインクをのせて刷る。
しかし中谷は「凹部と凸部の両方のインクを、一度のプレスで同時に刷り取る」という発想に到達した。
これにより、彫刻のような立体感と絵画的な色面が共存する、唯一無二の画面が生まれる。
- 土台には主に合板を使用。
- モチーフに合わせて合板を糸鋸で切り抜き、基本形(輪郭)を作る。
- その上から、木工用ボンドや寒冷紗、和紙、薄い段ボール、布などを貼り重ね、物理的な「凹凸」を形成する。
- 盛り上げた部分には樹脂(ボンド系、アクリルエマルジョンなど)を混ぜ、さらに強固な起伏をつくる。
- 表面にはニスやシーラーを塗布し、版としての強度を持たせる。
- 版全体に黒インクを刷り込み、凹部にインクを残す(凹版の原理)。
- 余分なインクを布で丁寧に拭き取る。
- 表面にはローラーで別の色インクを重ねる(凸版の原理)。
- 最後にプレス機で強い圧力をかけ、一度で紙へ転写する。
- 凹部の黒が深い陰影を生み、画面に重層的な奥行きが生まれる。
- 樹脂の起伏が紙に立体的に浮かび上がり、化石や遺跡のような質感となる。
- 切り抜かれた板の「かたち」がそのまま記号性を帯び、象徴的なフォルムとして画面に残る。
- 油彩画でも版画でもない、彫刻的な抽象世界。
- 1970〜80年代:合板の形を主役にした有機的フォルムが中心。
- 1990年代:凹凸をさらに複雑化し、異素材を貼り込む“半立体”へと進化。
- 1995年《碑(海・蠕動)》の頃には、複数の大板を組み合わせた巨大作品へ発展。
中谷の言葉に「版は手で触れるためにある」というものがある。
凹凸併用版は“触覚の版画”と呼べるほど、視覚だけでなく触覚的な魅力を持つ技法である。
II. ステンシルと自家製インク
1999年、胃癌の手術を受け、体力的にプレス機の操作が困難となった。
しかし中谷は制作を断念するのではなく、むしろ新たな技法を切り開く。
選ばれたのは「ステンシル(合羽版)」――型紙の“抜け”から絵具を落とし込む技法だった。
中谷はここに、十勝の大地そのものを混ぜ込んだ独自のインクを用いて、まったく新しい“土の絵画”を作り出した。
- モチーフに合わせた型紙を切り抜く。
- キャンバス地(布)や厚紙に型紙を貼る。
- 木炭粉・石粉・鉄粉・アクリル樹脂を混ぜた粘りの強いインクを、左官のようにコテで押し付ける。
- 型紙を外すと、彫刻的なかたちが現れる。
これらを練り合わせることで、油彩でも版画でも得られない独自の“重さ”と“乾いたざらつき”が生まれる。
- 木炭粉(池田町の炭焼き小屋から採取)
- 石粉(とのこ、白土)
- 鉄粉(錆を含む粉状の鉄)
- アクリル樹脂・アクリルメディウム
- 土(十勝の黒土を少量加える場合もある)
- 天然色料(赤土・黄土)
中谷にとって素材は単なる画材ではなく、 「土地がもつ記憶を画面に定着させる媒体」であった。
十勝の炭・土・鉄は、「火」「大地」「金属」といった原初的な要素の象徴でもあり、 作品に古代遺跡のような力強さが宿っている。
- 厚く荒い塗りによる、土壁のような肌合い。
- 赤錆色・炭黒・土黄が混じり合う重厚な色調。
- 「傷」や「ひび割れ」のように見える表面の凹凸が、生命の痕跡として立ち上がる。
- 凹凸併用版よりも“面”が強調され、より静謐で象徴的な画面構成へ。
III. コラージュによる拡張
1990年代以降、中谷は画面に異素材を貼り込む「コラージュ」を積極的に取り入れ、 作品を「平面から物体(オブジェ)へ」拡張していった。
- 紐・ロープ・網・布
- ハトメ・ワッシャー(鉄製リング)
- 鉛板・銅板・アルミ片などの金属
- 貝殻・砂・土・乾燥植物
- 紐……「図(形)」と「地(背景)」を結び、画面を横断する“記憶の線”。
- 金属片……時間とともに変色する素材で「風化」を象徴。
- 貝殻……生命の痕跡としての象徴的要素。
- 砂・土……大地の記憶そのもの。
中谷にとってコラージュは単なる装飾ではなく、
「作品のなかに現実の物質(=時間)を招き入れる行為」であった。
異素材の重みと歴史性は、ステンシルの荒々しいマチエールと響き合い、
作品を“平面の絵画”から“触覚的な記憶の装置”へと進化させた。
中谷有逸の技法は、単なる技術的工夫ではなく、
その生涯のテーマである「記憶」「時間」「風土」「生命」を形にするための方法そのものであった。
凹凸併用版による有機的なフォルム、
ステンシルによる土と鉄の画面、
そしてコラージュによって取り込まれた現実の物質――
それらすべてが「碑(いしぶみ)」という概念に収束し、
静かでありながら深い、普遍的な抽象世界を築き上げたのである。